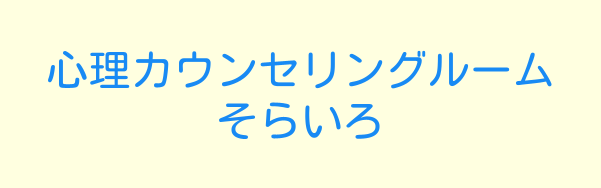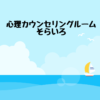不登校、ひきこもり、ニートを心理カウンセリングで改善、回復|神奈川 020401
2-4-1
このページでは不登校、引きこもり、ニートについてのご案内をします。
しっかりと回復、そして成長へつなげる支援を行っております。ぜひ、ご覧になってください。
このページの目次
1.はじめに
このページでは不登校、引きこもり、ニートについてのご案内をします。
言葉の定義なども含め整理をしながらお話を進めてみたいと思います。
不登校、引きこもりはなかなか回復事例が少なく、新規に不登校になる生徒は増加しているのが現状です。
このような状況下、そらいろのカウンセリングでは、慰め中心の傾聴対応ではなく、
しっかりと回復、そしてさらなる成長へとつなげることを目指しており、実現しております。
いろんなところでご相談なさってなかなか回復できないとお困りでしたら、ご遠慮なく、おっしゃってください。
不登校、ニート、引きこもり、いずれも当事者とご家族にとってつらい響きの言葉だと思います。
未来に向かっての時間の流れが、この状態によって立ち止まることになるからです。
しかし、心理カウンセリングルーム そらいろ では、この問題に
真正面から向き合い、なぜ、このような問題が発生するのか、そして、どうしたら、
回復するのかという問題に真正面から取り組み、多くの方の回復、成長をご支援致して参りました。
このページではその成果を踏まえ、皆さんに希望をもってもらえるように丁寧にお伝えしたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
2.不登校、引きこもり、ニートとは
第2章では、不登校、引きこもり、ニートについて理解をしましょう。
2-1.言葉の定義について
まずは言葉の意味を確認しておきましょう。
①不登校とは
不登校とは,何らかの心理的・情緒的・身体的あるいは社会的要因・背景により,
子どもが登校しない,あるいはしたくともできない状況にあることをいいます。
(ただし,病気や経済的理由によるものを除く)
②引きこもりとは
仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、
6か月以上続けて自宅にひきこもっている状態を「ひきこもり」と呼んでいます。年齢上限はなし。
③ニートとは
ニートという言葉はイギリスで生まれました。“Not in Education, Employment or Training”
という言葉の頭文字を取ったのがニート(NEET)です。
教育、雇用そして雇用訓練のどの状態にも所属していないという意味です。
日本では15歳から34歳までの若者のうち、学生でもなく、働いておらず、
仕事に就くための職業訓練も受けていない、つまり仕事をする意思のない人たちのことを表しています。
失業していても働く意思がある人や、正規雇用ではなくてもフリーターや
アルバイトという形で仕事をしている人はニートではありませんが、
いわゆる引きこもりの状態の人は、ニートに数えられます。
以上になります。ニートとは本来イギリスの制度の呼称であり、日本では若年無業者という言葉があるようです。
また、そらいろでは、ニートと引きこもりの定義が重なる部分があるため
わかりにくいので不登校と、引きこもりの二つの言葉を使用するように致しております。
2-2.不登校、引きこもりの現状について
そらいろの不登校、引きこもりのカウンセリングにおいては行き渋りから始まり、不登校になってしまうお子さんと、
社会人でありながら、あるいは就労年齢でありながら仕事ができない、引きこもりの方が主な対象になります。
不登校につきましては、小学生が一番多く、次に中学生、高校生、大学生の順番になっております。
統計データとしては
○小中学生の不登校
2010年 11.9万人 1.13%(全児童比)
2015年 12.5万人 1.26%
2018年 16.4万人 1.7%
2021年 24.4万人 2.4%
2022年 29.9万人 3.2%
2023年 34.6万人 3.7%
○引きこもりの方の数
2018年 15歳~64歳 115万人
2022年 15歳~64歳 146万人
2-3.初期対応が不適切だと本格的な不登校、引きこもりになる
不登校、ひきこもりにおいて大変ショッキングな事実があります。それは、
行き渋りの状態を本格的な不登校、引きこもりの状態に悪化させてしまう原因が、
親御さんの登校・出社への刺激にあることが多い
ということです。 えっ、と驚かかれる方も多いと思います。
しかし、お話をお伺いし、お子さんの心理分析を進めていくと、そうだった、と気づかれる親御さんが多いのです。
どういうことかをご説明しましょう。
実は行き渋りが始まったとき、すでにお子さんの心は、例えると複雑骨折状態にあるのです。
つまり、すでに学校や会社に行くことに対する自信が崩壊している
と言えるのです。しかし
親御さんはこの状態を勘違いされることが多く、自信が低下し始めている状態と思い込んでしまう傾向があるのです。
そのため、
今なら間に合う、本格的になるまえに、行かせる癖をつけないといけないと思い込んでしまう
ということが起きてしまうのです。この思い込みにより、一生懸命に刺激を与えることになるのです。
中には布団から引きずり出してまで、刺激を与える方もいらっしゃいます。
しかし、地震の崩壊状態で、この刺激を受け続けると
かろうじて 形を保っている自信が完全にバラバラの破片になってしまうこともあります。
これは最も残念なことなのです。
この状態に至ってしまった多くのご本人、ご家族の方を支えて参りました。そこからでも遅くはありません、
もちろん回復しますが、できたらそうならないように済めば、その方が良いですよね。
なので、このことを広く皆さんに知って頂ければと思う次第です。
3.一般的な取り組み
不登校、引きこもりに対する一般的な取り組みは以下のように実施されております。
リストの順番は、相談する順番とだいたい、同じになっております。
〇学校の先生に相談
〇学校のスクールカウンセラーに相談
〇行政の相談窓口
〇医師に相談
〇NPO法人、フリースクールなどへのご相談
〇心理カウンセラーへの相談
お気づきになられた方もおられると思いますが、案外心理カウンセリングは最後に近いのです。
これは、心理アプローチへのハードルが高いからなのかもしれません。
しかし、そのためか、心理学的な支援が行き届かず、お子さんの心を根っこから回復させ、
再発の心配のない支援に、ということには至っていないのが現状のようです。
4.そらいろのカウンセリングの特徴
4章では、
不登校、引きこもりの回復カウンセリングにおいて、そらいろで
大切にしている事について、お話ししたいと思います。
4-1.好ましくない接し方とは
まずは好ましくない対応を知っておいてください。効果がないどころか
むしろ悪化してしまう事もあります。
それは
①不要な刺激を与えず、穏やかに過ごしてもらう
ということと
②登校刺激を与え続ける
になります。
①の対策、広く一般的に実施されているこの方法では、現状安定にはなるのですが、
認知の修正、自信、自己愛の回復などが発生しないため、社会復帰、再度の登校には至りにくいのです。
そして
②の対策もまた、好ましくありません。徐々に悪化してしまう傾向にあるからです。
本質的な回復が発生していないということは、登校する自信は回復していないと言えます。
この状態で再登校すると、自信が復活していないので、再度、
傷つくことになり、折れてしまう事になります。
4-2.本質的な接し方とは。
本当に大切なことは、お子さんの心理状態を深く理解することなのです。
お子さんの心の状態に関する理解が進まないために、このままいくと、
どんどん甘えてしまうのではないかという一般論が優先となってしまいます。
そのため、登校刺激をすべきと考え、お子さんの気持ちがどういう状態かを
把握できないまま、登校させることが日常的になってしまうのです。
その結果、メンタルへの負担が大きくなってしまい、破綻に至ってしまう事例が多いのです。
一般的にはご本人がカウンセリングを受けてご家族は結果を見守る
というパターンになりますので、この状況が改善されないまま残ります。
そこで、そらいろでは、ご本人がカウンセリングをお受けになる場合であっても、
保護者の方のご相談の機会も同様に重要であると考えております。
お子さんへの接し方で注意をしたほうがよい点などを知って頂くため、
になります。ご家族の方が心理アプローチを理解されている場合の
ご本人の改善度は大分違います。
そのため、ご本人とご家族それぞれのカウンセリングを同時並行で実施していただくことをお勧めを致しております。
もし今、このページを、お子さんが行き渋りの段階で見られた方は、
ぜひ、一緒に心理状態を推測し、分析し、お子様の状態を予測して参りましょう。
そしてもし、過干渉になってしまっていた、と思う方もまた、
一緒に心理状態を分析し、推測してみましょう。
学校、自治体の相談コーナー、医療機関、様々なところにご相談されたのですが、
上記のようなことを教えてもらえなかった。
とおっしゃられる方も多いのですが、これには原因があるのです。
ご相談された担当の方が、回復までの支援を経験した方であれば、
自然に上記のような助言が出てくると思います。しかし、対応方法の
研修を受けたという方の場合、難しいと思うのです。
しかし、それでは、増え続ける不登校、引きこもりの方のご家庭にとっては困りますね。
このページを見て参考になったと思えたら、周囲の方のお伝えして頂ければと思います。
そらいろではこういった知識をできるだけ多くの方と共有できたらいいと思い、
勉強会などでもお伝えするようにしています。
宜しければご覧になってください。ページ下部に過去の勉強会の開催内容が掲示されております。
5.具体的なカウンセリングの流れ
第5章ではカウンセリング全体の流れと重要なポイントの解説を致します。
5-1.は全体の流れを説明しております。
5-2から5-6はカウンセリング中の重要なポイントになります。
5-1.カウンセリング全体の流れ
ここではカウンセリングの方法についてご説明します。
一般的にカウンセリングと言いますと、
電話カウンセリング
と
面談カウンセリング
がございます。
面談は開成ルームのほか秦野、厚木にて実施が可能です。
また、お電話につきましては、基本的にこちらからおかけしますので、通話料金をお気になさらずにお話し頂けます。固定電話、携帯電話ともにこちらからおかけします。
そのほかにも LINE 通話、Skype 通話、Google Meet 通話、Zoomなどの方法もご選択可能です。
また、カウンセリングを受けるのは通常、ご本人ですが、不登校やひきこもりでお悩みの場合、ご本人様がカウンセリングというのは難しい場合もございます。
そこで、そらいろでは、
〇クライアントさん自身が受ける通常のカウンセリング
と
〇保護者の方が代理で受ける、代理カウンセリング
が選択可能です。それぞれの特徴をお伝えしますので、ご参考になさって頂き、ご判断を頂ければと存じます。
5-2.クライアントさん自身が受ける通常のカウンセリング
この場合、ご本人さんが人とお話ができる状態であることと、面談の場合、移動ができることが前提となります。
〇メリット
ご本人が直接、カウンセリングで様々なお話ができますので、吐き出すことによる自浄作用や問題解決の方法論などを知ることができます。
〇デメリット
通常、カウンセリングでは守秘義務があるために、カウンセリングの内容をご家族にお伝えすることはありません。
そのため、ご家族のご本人に対して好ましくない接し方があったとしても、その部分を修正することが難しいという状態が残ることになります。
その影響を防ぐためには、ご家族の方がご本人とは別に対応方法などのご相談を受けて頂くことがお勧めになります。
5-3.保護者、おじ、おば、祖父母などの家族の方が代理で受ける、代理カウンセリング
〇メリット
ご本人が人とコミュニケーションをとれる状態でない場合や
あきらめなどによる回復への意欲が低下している場合、
対人恐怖感などによって外出が困難な場合、
更には、反抗的、暴力的で回復作業への着手が困難な場合に効果を発揮します。
しかも、カウンセリングをお受けになる方は当事者ではないために、
健全な場合が多いので、安定して回復の方法を話し合い、進めていくことが可能です。
また、ご家族の方が心理サポートの方法を学ぶことにより、お子さんは常に
心理サポートの影響を受けることができ、連続的なサポートを受けることができるメリットがあります。
〇デメリット
年齢が高校生くらいまではこの方法が望ましいのですが、大学生以降では、
最終的にご本人が来ていただいて、心の問題の解決とご卒業に至ることが必要になってきます。
そのため、ご本人がカウンセリングに直接通うためのきっかけづくりをする必要があります。
その具体的な方法については一緒に考えてまいりましょう。
5-4.カウンセリングのステップ~回復までの道順
カウンセリングの方法がある程度、イメージできましたら、いよいよ、カウンセリングに入ります。
カウンセリングの流れは次の通りです。
①原因の分析
②回復の方向性を相談の上決定
③回復の具体策の検討
④具体策の実施と進み具合の確認
⑤具体策の微修正の検討
⑥好ましい結果が出るまで③~⑤を繰り返す
好ましい結果が出ない場合、②を再検討します。
6.回復はゴールではない、それでは再発するかも
7.知恵とヒント集
次にご本人もしくは、ご家族の方、あるいは双方の無料お試し電話カウンセリングを行って頂きます。
そして、詳しい状況をお聞かせ頂き、回復までの方法についておおよそのご納得を頂きます。
ご日程を確定し、開始となります。