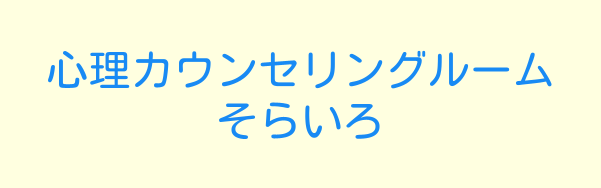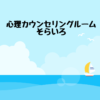児童虐待、育児放棄ネグレクトを回復、解決|心理カウンセリング 神奈川 020501
ページ番号 2-5
この相談事例は、虐待をしてしまう自分を何とか止めたい、という親御さんに向けて書かれております。
このページの目次
1.はじめに
児童虐待や育児放棄は、表に出にくく、誰にも相談できずにk加害者、被害者ともに一人で抱え込みやすい問題です。
しかし、心の中にある葛藤や不安は、安心して話せる場でこそ整理され、回復への道が開けます。
このページでは、虐待・育児放棄の背景や一般的な対応、そしてカウンセリングによる回復支援についてご紹介します。
ご一読頂き、何か感じるものがありましたら、ぜひ、一度お話をさせてください。
2.児童虐待、育児放棄の現状
ここでは児童虐待、育児放棄、ネグレクトに関する状況をまとめます。傾向として知っておいてください。
2-1.児童虐待、育児放棄に関する傾向
昨今の日本における児童虐待の現状は大変深刻です。児童相談所が対応する虐待相談件数は増加の一途をたどっており、
厚労省の統計によると、2022年度の児童相談所への通報件数は21万9,170件。
前年度より11,510件(5.5%)増加し、過去最多を更新しました。
虐待の種類は以下の通りです:
心理的虐待:約59%
身体的虐待:約24%
ネグレクト(育児放棄):約16%
性的虐待:約1%
このように、ネグレクトも含めた深刻な状況が社会全体の課題となっています。
3.児童虐待、育児放棄の対応について
3-1. 児童虐待、育児放棄に関するお悩みの事例
児童相談所や自治体の相談窓口には下記のようなご相談が寄せられているようです。
・つい怒鳴ったり、手を出してしまう。
・子どもの世話が重荷で、避けたくなる。
・子どもが泣く声にイライラしてしまう。
・自分の育児が間違っている気がして苦しい。
・周囲に相談できる人がいない。
心理カウンセラーのところに寄せられるご相談も同じようなことが多いものです。
ただ、心理カウンセラーのところにご相談をされると違うところがあります。それは、心理アプローチが専門のため、
一般的な対応の他に、どうしてそうなってしまのか、原因や背景についても深く分析をし、ご理解を頂くことができます。
そのため対策も根本的に解決が望める対策を立案することが可能になります。
3-2. 問題の背景について
虐待や育児放棄の背景には、親自身が虐待の経験を持つ
・育児への孤立感、孤独感
・経済的、精神的なストレス
・サポートの欠如
などが複雑に絡み合っています。
また、虐待が発生している時の心理状態だけにとどまらず、加害を行ってしまう方の
過去におけるトラウマ体験なども含めて丁寧に振り返る必要があります。
場合によっては、加害を行ってしまう側の方自身がとても深刻な被害者であった、ということもありますが、
心理カウンセラーによるケアがない場合は根本療法的な対応というよりも対症療法的な対応になりがちです。
3-3.解決の方向性
解決の第一歩は「話せる場所」と「理解者」に出会うこと。
感情を安心して表現できる環境で、心を整理し、親自身が回復していくことが大切です。
心理カウンセリングは、そのための有効な手段です。
4.そらいろのカウンセリングの特徴
そらいろの虐待、育児放棄ネグレクトに関するご相談の特徴はなんと言っても、
〇心理学を活用したノウハウにより、しっかりと現状の分析を行います。そのため、深く、広い範囲の状況を
より正確に分析し絞り込む子ことができます。
〇対策もまた、心理アプローチによる対策を中心とするため、暴力を振るわない工夫という表面的な対策
だけではなく、根本的に性格的成長も含めての対策を立案します。
〇被害を受けたご家族の方のトラウマの回復などもしっかりと行い、軽減できるようにお手伝いをします。
保護者さま、お子様どちらのお立場の方も、傷を癒したり、我慢ができたり、という事の他に、
根っこからの幸せを実感できる人生を実現できることを目標にしたお手伝いを心がけております。
5.具体的なカウンセリングのながれ
この章ではカウンセリングの具体的な進め方についてご説明致します。
5-1.は全体の流れを説明しております。
5-2から5-6はカウンセリング中の重要なポイントになります。
5-1.カウンセリング全体のながれ
①先ずは親御さんの辛いお気持ちをじっくりとお聞きいたします。
②そして、親御さん自身の辛い過去の体験、今のお悩みなどを整理します。
③上記を整理し、どうして子どもに対して虐待をしてしまうのか、原因を見つけていきます。
④カウンセリングを通じて、ご自身の問題を考え、一緒に解決して行きます。
それと同時にお子さんへの接し方、育児の仕方をやはり一緒に考えます。
虐待をしてしまう親御さんの辛さを理解し、お子さんと良好な関係を再構築し、
ご自身も幸福感に溢れた家庭を作る幸せを体感できるように一緒に考えて見ましょう。
虐待で悩んでいる親御さんはその事をどうしても周囲に相談し難いのが現状でしょう。
安心してご相談なさってみてください。
5-2.できるだけ、様々な感情を吐き出しましょう
初期の面接(インテーク面接)が終了しましたら、いよいよカウンセリングの開始になります。
カウンセリングの中心的な部分にもなりますが、心に蓄積した様々な思いを開示してみましょう。
開示することがなくなるくらい、なんでも話していただけると、とても良いことです。
開示率が向上するかどうかは人間関係性が安心であるかどうか、信頼性が高いかどうかによります。
ということは開示度が高いとそれだけ関係性が成熟したと言えます。開示度のみが独り歩き
してはいけませんが、大切なポイントの一つです。たくさんのことを開示できますと、
今後のカウンセリングにおいて、心の傷を小さくしたり、自信を育てたりするための鍵
となる部分が見つかってきます。開示度というのはとても大切と思ってください。
5-3.センサーの回復を意識しましょう
私たちの心には、
〇これ以上我慢したら不健全になってしまいますよ
〇もう我慢の限界ですよ
と教えてくれるセンサーがあります。
しかし、メンタルが病んでしまう方は、大抵このセンサーが機能していないのです。
つまり火災報知器があってもスイッチが入っていないようなものです。このスイッチを入れなおす必要があります。
そしてお子さんのセンサーは大人程、しっかりと働いてくれないので、本人が病んでしまう
くらい、我慢をするということが頻繁に発生します。
ある日、突然、学校に行けなくなった、ということがあった場合、この日まで周囲の人が
お子さんの心の警告ランプがついていたことに気づけなかったということになります。
つらい、苦しいと心の叫びが聞こえるようにしなくては問題の改善、回復、解決は難しいものになります。
そこで、このこのセンサーのスイッチを入れる取り組みが必要になります。
何度も振り返りながらの取り組みになりますが、この部分はとても重要ですので、丁寧に取り組みます。
5-4.認知の歪みを見つけて修正しましょう
認知の歪みを見つけだし、修正するステップです。
ここでは認知が歪んていると思えるところを見つけだし、本来どのように感じたら自分としては好ましいのか、
健全なのかをカウンセラーと話し合って参ります
このプロセスはとても大切なプロセスですが、地味な作業でもあります。
日常的な対人関係の中から歪みを見つけだし、一つ一つ修正を加えるという作業になります。
最初は途方もない作業と思われがちですが、結果としてはこの方法が早期の回復には効果的であることを、
回復した多くのクライアントさんが語ってくださっております
5-5.回復しにくい心の癖をみつけましょう
心理カウンセリングを通じてクライアントさんの認知の修正に取り組んでいると、
頑張っているわりに改善が進まないという事態が発生します。
こうなる原因を心の癖と呼びます。
具体的には、今まで習慣として身についてしまった思考癖です。この思考癖を理解しないと、
自分が、なかなか改善しないことを責めるようになってしまいます。
認知の歪みを理解し、ポジティブシンキングなど新たな思考癖が刷り込まれると
減ってきますが、このことを理解せずに何度も失敗したりすると、必要以上に自分を
責めるようになってしまいます。あくまで大切なことは原因の理解と今後の対策になります。
なので間違えても責めることをしないようにしてください。
新たな、健全な癖が刷り込まれたら、全体の改善も順調に進むようになります。
一つ、お願いしたい注意事項があります。
それは、
回復するための対策に過度に集中しない
ということです。
対策を行えばよくなると思われがちですが、本来の回復は精神面のバランスが
総合的に良くなることであり、それを成長と呼びます。
①健全なキャラクターを育てる
②自分の自発性もしくは主体性を育てる
③健全な協調性を育てる
上記が大切な要素であり、これにより自分らしさを育てる事になります。
根っこから回復させることこそ、真の改善、回復、解決であると思ってください。
5-6.自己愛、自信の回復、育成
健全な自己愛が回復もしくは育成できて初めて、問題の再発の可能性が下がります。
一度、この状態になれば、おそらくですが、自分やお子さんが病んでしまう状態を
回避できるようになると思われます。
自己愛というのは、生育環境によって育ちますので、育っていた方が元の状態になることを
回復といい、もともと育っていなかった方が一定の健全度になることを成長と言います。
多くの場合、カウンセリングによる心理的支援をここまで実施すれば、もう安心です。
また、自信についても、
自分なら、もしくはお子さんなら、きっと大丈夫、失敗しても周囲に相談しながら乗り超えることができるだろう
と思えたら、
自信もしっかりとしてきたことになります。
病や問題の起きていた前に戻るのではなく、前以上に明るく、可能性に満ちた状態が実現する可能性が高いのです。
6.カウンセリングのご卒業について
カウンセリングは、いつ頃卒業するとよいでしょうか。これはよく質問されることです。
大まかにお伝えしますとタイミングとしては三つあると思います。
①大変つらい状況が緩和された状態のとき。 感情は-2くらい
②回復ができたと思えたとき。 感情は±0くらい
③自信が回復し、自己愛が成長できたとき。 感情は+5くらい
一般的なカウンセリングで多いのは①の時ですが、再発の可能性がとても高いご卒業の時期でもあります。
また、②の状態でも過去の認知の歪みの修正は終わってなく、プラス思考が定着した状態ではないのです。
ですので、③が望ましいと言えましょう。今が幸せと実感ができ、この状態を続けたいと思える、
そして、プラス思考が癖として定着していると実感できるときこそが、最もおすすめするご卒業のタイミングです。
7.資料とヒント
7-1. 子供の虐待とは
児童虐待防止法では
「保護者が監護する児童に対し、暴行やわいせつな行為、長時間の放置や心理的外傷を与えること」と定めています。
子供の虐待には次の4つのタイプがあります。
①身体的虐待(全体の約5割)
殴る、蹴る、たばこの火を押し付けるなど、生命・健康に危険のある行為
②ネグレクト(保護の怠慢、拒否)(全体の約4割)
病気やけがをしても適切な処置を施さない、乳幼児を家に置いたまま度々外出する。極端に不潔な環境で生活させるなど、健康状態や、安全を損なう行為。オムツを1日交換しない、などもこれに該当します。
③心理的虐待(全体の約1割)
子供の心を傷つけることを繰り返し言う、無視する、ほかの兄弟と著しく差別的な扱いをするなど、心理的に傷つける行為。
④性的虐待(全体の数%)
子供への性交や性的行為の強要、性器や性交を見せるなどの行為
以上が主な虐待のタイプとされています。虐待というと身体的な虐待がイメージされると思いますが、ネグレクトが4割あるという事はとても驚きであります。
7-2. 虐待の現状
相談件数(全国の児童相談所)
1990年度 1,101件
2005年度 34,451件
2019年度 193,780件
2022年度 219,170件
と、非常に増加しております。
また、主な虐待者は
●母親 約6割
●父親 約3割
●その他の親族 約1割となっています。
やはり、お母さんが一番接しますので、お母さんの比率が高くなっております。
しかし、お母さんだけの問題ではなく、むしろ、お母さんのことを理解してくれないお父さんに原因があったり、
舅(しゅうと)、姑(しゅうとめ)さんの不理解や経験の押し付けが原因だったりする事もありますね。
決してお母さんだけの問題ではないと捉えたいと思います。
7-3. 虐待における一般的な対応とは
児童虐待に対する一般的な対応は、早期発見・通報・保護・支援を柱にして、
行政・学校・医療・地域住民など多くの関係者が連携して行われます。以下に代表的な対応を紹介します。
①早期発見
虐待は表面化しにくいため、小さな異変に気づくことが重要です。
学校や保育所:子どもの様子やケガ、不自然な行動、欠席の増加などをチェック。
医療機関:不自然な傷や発育不良に気づいた場合は対応。
近隣住民・親族:家庭内の叫び声や子どもの異常な様子に注意。
②通報
虐待の疑いがある場合、通報義務があります(児童福祉法第25条)。
通報先は主に 児童相談所全国共通ダイヤル「189(いちはやく)」。
通報者の匿名性は守られ、責任を問われることは基本的にありません。
③子どもの保護
通報を受けた児童相談所は、以下のように対応します。
家庭訪問や聞き取りを通じて事実確認。
一時保護所への保護(緊急性が高い場合)。
医療機関やシェルターとの連携。
④親への支援と指導
虐待の再発防止には親への支援も重要です。
家庭訪問・カウンセリング。
子育て支援プログラム(親教育)への参加。
経済的な困窮など、背景要因への福祉的支援。
⑤子どものその後の支援
里親や児童養護施設での生活支援。
心のケア(心理カウンセリングやPTSD支援)。
学業・生活面でのサポート。
⑥地域や社会の役割
子育てに関する悩みを相談できる場の設置(子育て支援センターなど)。
地域ぐるみで孤立した家庭を見守る体制の構築。
児童虐待防止キャンペーン(オレンジリボン運動など)。
7-4. 子どもの虐待はなぜ起きるのか?
ここでは子供の虐待が発生する背景を見つめてみましょう。
〇夫婦の不和
〇仕事のストレスに苦しんでいる
〇望まれない子ども
〇癇癪(かんしゃく)もちで、なだめにくい
〇親自身が子どもの頃に虐待を受けたために子どもへの接し方がよく分からない
などが列挙されます。
それとは別に、背景として
○子育てを行う親が孤立してしまっている
○子育てに自信がないのに誰にも相談できないという不安感、焦燥感
虐待をする親はひどい人だと思われがちですが、 親自身も悩み苦しんでいるのです。
親を責めるだけでは何の解決にもなりません。 虐待は親からのSOSでもあるのです。