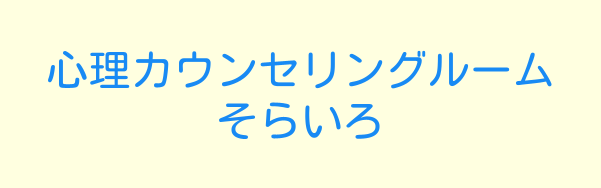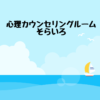育児・子育てが楽しく幸せになる考え方、知恵
ページ番号 2-3-5
このページでは、育児、子育てが大変、つらい、苦しいという方にぜひお伝えしたい、考え方や知恵をご紹介したいと思います。
育児だけでなく人生まで好転させることができるかもしれない考え方です。
日々のカウンセリングで感じたことを一つ、一つのお話にまとめ、ご紹介をします。
なるほどと思ったらぜひ、日々の行動に活かしてみてください。
よくわからない、と思ったらぜひ、ページ下部よりご質問ください。
このページの目次
- 1. 1.はじめに
- 2. 2.考え方、知恵、ヒントの具体例
- 2.1. 2-1.育児、子育てと教育を使い分けましょう
- 2.2. 2-2.子育てと教育のバランスとは
- 2.3. 2-3.行動を管理すること、心を管理すること
- 2.4. 2-4.これからの育児、そらいろ流、育児、子育て論
- 2.5. 2-5.健全な協調性とは
- 2.6. 2-6.子育てのゴールとは
- 2.7. 2-7.子育てのゴールとは 船長を育てる編
- 2.8. 2-8.育児ノウハウは育児を楽にしません
- 2.9. 2-9.正誤にこだわる子育て
- 2.10. 2-10.育児ノウハウよりも、育児哲学が大切です
- 2.11. 2-11.子育てにおいて育てるべきもの
- 2.12. 2-12.子育てを取り巻く環境
- 2.13. 2-13.育児を楽にできる考え方
- 2.14. 2-14.考え方その1 まずは母の人格の尊重から
- 2.15. 2-15.考え方その2 4階建ての1階が大切
- 2.16. 2-16.考え方その3 1/5の論理
- 2.17. 2-17.考え方その4 母性と父性のバランス
- 2.18. 2-18.考え方その5 最高の育児ノウハウは夫婦円満
- 2.19. 2-19.工事中
1.はじめに
そらいろの心理カウンセリングやメンタルトレーニングをご卒業された方の多くは、
〇育児ってこんなにシンプルだったんだ。
〇育児するのがたのしくなった
〇子どもが明らかに変化した
とおっしゃられます。
〇お母さんがとっても楽になれて
〇お子さんが自主性がぐんぐん育ち
〇お子さん心が強く前向きになり
〇お母さんの心も強くおれにくくなる
〇そして家族が幸せになれる
このような状態が実現できたと言う事は育児が楽になっただけでなく、生きることも含めて、楽になった、充実した、
と言えます。ここまでくるには様々な気付きがあったことと思います。皆さんの気づきを教えて頂き、
気付きの過程で得たものを知恵としてまとめ、お伝えして参ります。ここに書いたことは一部のクライアントさんだけが
できるようになったのではなく、あきらめずに進んだクライアントさんは皆さん同じようにおっしゃられるのです。
決して特別な能力や努力は必要ないのです。多くのクライアントさんが苦労して掴んでくださった
考え方、知恵、ヒントを以下にご紹介致します。
2.考え方、知恵、ヒントの具体例
2-1.育児、子育てと教育を使い分けましょう
私たちがなんとなく使っている言葉ではありますが、案外大きな意味の違いがあるのではと思っています。まず、育児と子育てについて
◎育児とは 主に幼児期までの子供を育てること。
◎子育てとは、お子さんの年齢にかかわらず、親が子を育てることを言う。
という違いがあるようです。そして、その先が大切です。
●育児、子育てとは本来の子供の性格を育てること
●教育とは心を育ているよりも、知識や技能を育てることが中心となる。さらにはすべての人が訓練されるとできるようになる。
という違いがあるのです。つまり、子育ては本来、個性を育てるものであり、その個性を基本に信頼関係や協調関係を育てるものです。
また、教育はみんなができることを自分もできるようにするというものになります。つまり育てるところが違うのです。
育児、子育ては性格の基本である個性【キャラクター】を、そして、教育は個性の外側にある、グループの中での役割を認識して行動する能力【パーソナリティ】を育てるのです。
最近は子育てをしている時間がどんどん減り、家庭内でも教育をしている時間が増えているのが気になります。
2-2.子育てと教育のバランスとは
子育てと教育はどうバランスをとるのが良いでしょうか。幼児英才教育では子育ての部分を抑えて、教育を強化していきますね。
同様に早い年齢から習い事をすると個性が抑圧されて、良い子には育ちますが、自分らしさがわからない大人に成長することになります。
これは早期教育の怖い所でもあります。実際に、不登校、引きこもり、精神疾患、人間関係に問題を抱える方の多くは、
子育てを抑えられ、教育を強化された成育環境
において、自分らしさを抑制され、それが抑圧に発展される、という経験をされているお子さんが多いのです。
ではバランスはどうとるのか。
a.十分に子育てを実施し、キャラクターを育てる。母子の信頼関係も育てる
b.その次に教育に着手し、パーソナリティを育てる。父子の信頼関係を育てる
c.その上で自分の個性と、団体での役割を学ぶ協調性を育てていく
→自分をつぶさず、他人もつぶさない、幸せな妥協を見いだせる力を育てる。
この順番でバランスが取れたらいいのではと思います。心配なケースというのは、育児がしっかりできてないのに、教育をしっかりと実施し、
子供が自分らしさを育てるよりも、他社が設定する目標をクリアーすることこそ、人生であるべき姿だと思うことです。
これは洗脳に近いパターンでありまして、お子さんが不登校になるなどで破綻しないとわかりにくいのです。バランスは大切ですね。
2-3.行動を管理すること、心を管理すること
カウンセリングにおけるお悩みの多くは子供の行動を管理できないという内容が多いものです。例えば
●時間に間に合うように支度ができにない
●片付けができない
●順番が守れない
●お友達とうまくコミュニケーションがとれない
などです。これらのお悩みは行動面の管理が難しいということになります。
そして次の展開は
●どうしたらできるようになりますか。
となるのが通常です。この場合抜け落ちているものがあります。それが心の管理です。そもそも、どうしてそうなるのか、
心理的な背景を探るというステップが抜けてしまいがちなのです。そうなるとどうなるのか、それは
心を見ないで行動だけをできるように接していきますので、お子さんに、いつの間にか心を抑えて行動する癖がつき、
初めは抑制だったのに、いずれは抑圧になっていきます。
抑圧とは無意識に抑制することを言います。つまり、自動的に自分の心を抑える状況が出来上がってしまうのです。
そこでよく聞かれる言葉が
そこまでケアしている余裕はありません。
という言葉です。
しかし、実はそのまま時間が過ぎていくと、反抗だったり、不服従が増えてしまい、反って大変な状況を作り出してしまうことが多いものです。
どうしてそうなってしまうのかを考える、心の管理を大切にしたいものですね。
2-4.これからの育児、そらいろ流、育児、子育て論
そらいろ流と名付けてますが、誰も知らなかったことを発見したということではないのです。カウンセリングを実施していて、
この方法がいいのではと思いついたものを、なにか呼び方があるといいな、と思い、呼び名をつけてみました。
しかし、内容を読んでいただくと、今までの育児方法では子供が良く育たない理由がはっきりとしてくると思います。
早速ですがご説明を始めたいと思います。
カウンセリングルーム そらいろ では、ここ数十年の育児、子育ては大きな流れの変化があったと考えております。
日本において、ここ数十年の間を除けば、どの時代にも、不登校だったり、引きこもりということが社会問題になったということはありませんでした。
この数十年の間に発生した変化について、そらいろでは、
それでは、一体何が起こっているというのでしょうか。
まず、今、学校、職場などに適応できないお子さんの共通点を見つけてみますと、
〇協調しすぎて、自分がつらくなっている
〇しないといけない、というような強迫観念を持っている
〇受容しすぎて自分がつらくなっている
〇もしくは自分が主張しすぎて気まづくなってしまう
等の子供たちが増加傾向なのです。これでは不登校も発生しますね。このような状況になってしまうと、
子ども達の社会適応力の低下につながるのです。
ではなぜ、このような状況が発生したのでしょうか。それは、
〇早期の幼児教育が原因であると考えられます。
早期に育児が終了し、教育に移行してしまいますと、子供らしさを育てることができる時期が短期間で終了してしまいます。
そのため、子供たちはごく早い年齢から、あるべき姿を追い求めることを要求されるようになります。
その結果、常に個性よりもあるべき姿を優先する癖がついてしまい、あるべき姿に近いかどうかをいつも気にするようになります。
しかし、実際には自分たちの周囲に、あるべき姿とは遠いけど、確かに存在感のある人が何人もいて、この人達に適応ができなくなっていくのです。
その結果。あるべき姿に近い人、もしくはあるべき姿を一緒に目指す姿勢のある人には適応ができやすいのですが、それ以外の
個性的な人には適応が難しいという状況が生まれてきます。これはかなり衝撃的な事ではないでしょうか。
つまり、最近の育児では、具体的な人をイメージしてコミュニケーション能力を高めるのではなく、あるべき姿に近い人を目指して
コミュニケーション能力を向上させる訓練を行うため、実際の個性ある人にはコミュニケーションを適応することが難しくなるのです。
私たちはあるべき姿を意識することはあっていいと思いますが、実際に存在している人にコミュニケーションを行い、その人達を受容し、
適応できることが大切と、考えております。
2-5.健全な協調性とは
2-6.子育てのゴールとは
育児、子育てのゴールとは ゴールはキャラの発揮、パーソナリティの学習。そしてバランス。
2-7.子育てのゴールとは 船長を育てる編
キャラクター
教育とは、お子さんの所属する団体のなすべきことを身に着けること
そしてバランスとは、どちらに偏ることなく、場面に応じて使いわけ、健全に生きる 術を身に着けることを言います。
-6. 最後に
○そらいろが目指すカウンセリングのゴールはまとめて表現すると
親子ともに幸せになれる。ということ
ご連絡先はこちらです
2-8.育児ノウハウは育児を楽にしません
現在は人類史上最も育児ノウハウが入手しやすい時代となっております。書店、セミナーなどで豊富に素晴らしいノウハウが入手可能です。このことはとても好ましいことのように感じられますが、問題はその結果です。
そのノウハウが豊富な時代に育つお子さんは、年々素晴らしい状況になっているのでしょうか。
残念ながら答えは否となります。
最近は、若者のメンタルの弱さは多くの人が指摘するところですし、中学生以下の不登校も全国で13万人ほどと、高水準を保っております。つまり、悩みを抱えるお子さんの数はむしろ増加傾向にあるのです。なにか矛盾のようなものを感じます。
2-9.正誤にこだわる子育て
今の時代、正誤的価値観が育児の中心軸になり、多くのお母さまが子供にしっかりと成長させたい、
失敗させたくない、そして、自分の育児も失敗したくない、ということで子供に接するので、いつの間にか、
育児ノウハウを積極的に取り入れた育児となり、書籍籍に書いていることを中心に育児が進められていく状況となりつつあります。
しかし、あまりに正誤にこだわると、お母さんの個性の反映がなくなりつつあり、
誰が育てているのかよくわからない育児になってしまうことが多いのです。
この現象を突き詰めていくと、人が人工知能化していることになります。
ソフトバンクから販売されている人工知能型ロボットにペッパー君(2015年発売)というロボットがありますが、
旅行に連れていき、人間と同じように運賃を払って交通機関に乗せる方がおられるそうです。
まさに人工知能と暮らす時代がそこまで来ております。
しかし、自分の育児が自分の個性を反省していないとしたら、もしかしたら、その育児は
ペッパー君が行っても変わらないものになってしまうのかもしれません。
上手、下手、つまり正誤にこだわるよりもお母さんらしさがしっかりと反映されている育児を心がけたいですね。
2-10.育児ノウハウよりも、育児哲学が大切です
会社の人材教育を見てみましょう。上司が成熟していると部下も育ちます。
お母さんの成長度がお子さんの成長度に影響します。
→大切なことはお母さんの業績ではなく、お母さんの哲学であり、人柄。
→心理学は心の理解、 哲学は上手に生きる知恵を学ぶ
2-11.子育てにおいて育てるべきもの
○育てるべきものはIQだけで十分でしょうか。EQも大切です。
→育児のゴールは船長を育てることにあります。
→船長とは人生を航海に例え、自分丸のために主体性を持って交渉しながら切り開いていく人を言います。
○5歳くらいまでは、感覚を中心に育つ、思考はそれ以降ですが、年齢が低い時から思考を使う子供が増えている。他人の顔色を見るお子さんの増加
○他人からの評価ばかり気にして、自分が自分を評価することができない状況。自分が自分を評価し、認められる、信じられる事を自信という
○繰り返しのPDCALにより、お母さんもお子さんも成長する
PLAN計画 DO実施 CHECK評価 ACTION対策 LOVEほめる
2-12.子育てを取り巻く環境
○1980年代以降、お父さん、お母さんが仕事の成果で評価される人事評価の影響を受けてきています。できる人が収入も多くなりますが、実際には減額されたり降格されたりする人が増えています。
非正規労働契約を更新されない方も、多くいます。このような状況下、成果が出ないと未来がないと思う大人の方も増えています。
→その結果、親心としてより若いうちから様々なことを教え、成果を出せるようにしよう思う。これが過干渉、過保護の温床となる
○過干渉、過保護により自分で判断できなくにくくなります。お子さんは過保護、過干渉に対処するために、エネルギーを使うようになり、自分の価値観による試行錯誤ができなくなり、自立度が向上しなくなります。
◯学力偏重社会から、メンタル力偏重に傾きつつある。採用試験や面接でも人柄を重視する企業が増えていると聞きます。
2-13.育児を楽にできる考え方
育児や子育てだけことではありませんが、物事をうまくこなせる人には共通の考え方があります。
それは、うまくいく考え方
別の言い方をすれば成功哲学のようなものであり、ここでは育児哲学、子育て哲学とも言えます。
その考え方をご紹介したいと思います。
具体的な育児テクニックも大切ですが、もっと大切であるのが、この考え方になります。
2-14.考え方その1 まずは母の人格の尊重から
育児、子育てをするにあたって、一般的には、育児教室とか、育児本、ネットの情報などを参考にしながら
育児、子育てを検討し、組み立てていくことになると思いますが、これらの情報をしっかりと行えば行うほど
失われるものがあります。それは、お母さんの個性を活かした育児です。
もし、ノウハウ通りの育児が最高の育児であれば、将来、人工知能を搭載した二足歩行の
女性型ロボットが開発されたりしたら、育児はこのロボットが行ったら最も良いということになってしまうかも
しれませんね。しかし、これでは申告な問題が生じてしまうのです、確かに生育環境にともなうトラウマなどの
発生は起きないと思いますが、人間関係性というものが形成できにくい状況になる可能性があります。
人間関係というのは、あくまでも個人と個人の個性のぶつかり合いから生まれるものです。
これがノウハウ通りのあるべき姿育児であると、個性と個性のかかわりではなく、個性と理想のかかわり
になっていきます。こうなると、人間関係性に苦手意識を持つ子供が育ってしまいます。
最近は子供たちだけでなく、大人でも、人間関係性に悩む方が増えております。これは、理想に近づけすぎる育児が
原因かもしれません。本来の望ましい育児、子育てというのは、実はこれができてないいけない
という基本的なルールみたいなものがあります、それは
お母さんの人格が尊重されている育児
ということになります。
お母さんには、元気な方も、おとなしい方もおられます。人格的に個性があるのに、育児の方法は一緒
というのはむしろ不自然なのです。それでは、社員教育と同じになってしまいます。
育児子育ての基礎は育児であり、教育ではありません。
お子さんの心を育む際に、お母さんの人格が尊重されていないと、誰が育てても同じになってしまいます。
それでは、人工知能がそだてるのと差がなくなります。あくまでお母さんの人格が尊重され、肯定的であることが
育児、子育ての大切な部分でもあり、無理せず、取り組めることにもつながるのです。
2-15.考え方その2 4階建ての1階が大切
○4階建てのお母さん一階を増やす
1階 自分自身、 2階 妻、 3階 母、4階 会社、地域の自分
2-16.考え方その3 1/5の論理
◯1/5の論理 閾値の話
1/1 1/5 2/10 3/15の差の意味
→インプットよりアウトプット
2-17.考え方その4 母性と父性のバランス
○育児は母性と父性がそろってバランス
母性とは、癒し、共感、優しさ 試合に負けて慰める
父性とは 成長の意欲、技術、 試合に勝つ練習をする
2-18.考え方その5 最高の育児ノウハウは夫婦円満
○夫婦円満こそ、育児ノウハウに勝る最高のノウハウとも言えます。
夫婦の人生哲学がとても大切、シングル子育ての場合は父性が少なくなってしまうことを、遠慮せずに誰かに補完してもらいましょう。
→部活のコーチ、親戚のおじさんなど。
2-19.工事中
○田んぼの田の話、マンション高層階の話、ハグの時間の話