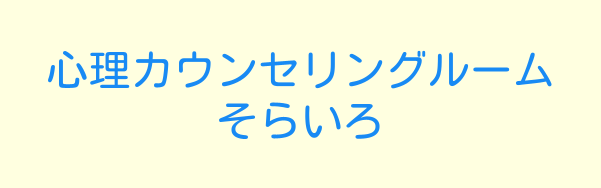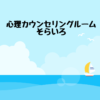講座 そらいろ心理学講座のご案内 神奈川 040103
講座番号:023
ページ番号:4-1-3
このページはそらいろ心理学講座についてご説明します。ご一読頂き、お気軽にご質問なさってください。
このページの目次
1.はじめに
産業革命以降、精神を患う人は一気に増加した
という説があります。自分のペースでなく、ライン全体のペースに合わせて作業をするため、
自分のペースとは違うペースで長時間にわたり、無理して働くことによるストレスが原因と言われています。
合理性の向上が過度に進むと、心に悪影響が出るということを教えてくれていると思います。
このページでは、教科書で学べる心理学とはちょっと違う、日常生活のいろいろなお悩みを解決してきた、実践的な
心理アプローチを学ぶことができる、
そらいろ心理学講座
のご説明を致します。
お悩みや精神疾患の回復のみならず、仕事、恋、家庭、子育て、プライベートなどの場面で
人生のマイナスの側面を減らし、
プラスの側面を増やしていくことを目指す、
そのような講座です。
2.心の関わるお悩みの現状
心、あるいは精神面に関わるお悩みと言いますと主に以下のようになると思います。
①対人関係のお悩み、(夫婦、家族なども含む)
②人前で緊張してしまう
③マイナス思考癖がひどく、常に未来が暗いと感じてしまう
④自分に自信がもてない。明るい未来もイメージできない。
などがご相談を受ける上で多いお悩みです。これらのお悩みについての背景に少し触れてみたいと思います。
現代社会では、私たちの心は日々多くのストレスや葛藤にさらされています。
仕事や家庭、人間関係、人生の目標、自己肯定感、将来への不安など、「心」に関わる問題は年々複雑化し、多様化しています。
例えば職場では、人間関係のストレスや評価への不安、成果主義によるプレッシャーなどが原因で、
知らず知らずのうちに心が疲弊していきます。また家庭においても、育児や介護、夫婦間のすれ違い、
孤独感や疎外感などが、慢性的なストレス源となっている方も少なくありません。
近年では、SNSやネット上のつながりによる“情報疲れ”や“比較疲れ”も心のバランスを崩す要因となっています。
自分の生活を誰かと比べては「自分は足りない」「もっと頑張らなくては」と無意識に自分を追い込んでしまう。
こうした傾向は、特に真面目で頑張り屋の方ほど顕著です。
また、「なぜかうまくいかない」「自分が嫌い」「繰り返し同じことで悩む」など、
原因がはっきりしないけれどモヤモヤとした不快感や虚無感を抱えている方も多くいます。
こうした状態は、表面的には大きな問題がないように見えても、
内側では深刻な孤独や自己否定感が蓄積していることが少なくありません。
子ども時代の家庭環境や、周囲との関係性の中で身につけてしまった“思考のクセ”や“心のブレーキ”が、
大人になっても無意識のうちに行動や感情の制限となっていることもよくあります。
たとえば、
●人に頼ってはいけない
●感情を表に出してはいけない
●いい子でいなければ愛されない
といった信念が、自分らしく生きることを難しくしています。
さらに、心の問題は、身体的な症状となって現れることもあります。頭痛や胃痛、不眠、動悸など、
一見すると身体の不調に見えても、その根底には心理的なストレスが関係しているケースも少なくありません。
このように、現代人の多くが、何らかの形で「心理的な問題」と日々向き合っているにもかかわらず、
●誰に相談していいか分からない
●こんなことで悩んでいる自分が恥ずかしい
と感じ、声を上げることができずに苦しんでいるのが実情です。
そらいろ心理学講座では、こうした悩みを持つ方が、
●自分を知ること
●自分をいたわること
●新たな視点で物事を見ること
を通して、心の深い部分から回復し、自分らしく生きる力を育むことを目指しています。
3.一般的に行われている対策と現状
上記のようなお悩みに対して、一般的に行われている対策は対症療法的なものが多いようです。
多くの場合、成功している人、そこから回復した人はこうした、という成功談を参考にし、
どのような対策を行ったかをまとめてお勧めのノウハウという形が作られているようです。
この方法論自体に問題はないのですが、方法論のみでの問題解決には限界があるということが重要です。
心理分析や背景の分析などが行われていない場合、技法優先の考え方になってしまい、
いろいろ試すけど具体的な成果が出にくい。という状況になってしまいます。
例えば、友達と深く付き合えない、という人に、プレゼントをしたら、というのは一つの方法論です。
良い面もありますが、問題があった時にお互いの心を尊重する解決ではなく、
プレゼントやイベントで水に流すのみの和解方法だけですと、本質的な問題の解決にはなず、信頼関係は育たなくなります。
心理面も含めた根本的な解決が必要とされるのですが、なかなかここが難しいところとなります。
そこで、そらいろでは上記を踏まえた講座を考案致しました。以下にご案内致します。
4.そらいろ心理学講座の特徴
⑴ そらいろ子育て心理学講座とは
そらいろ子育て心理学講座は、子育てに悩みや不安を抱える保護者の皆さまが、心理学的アプローチを通じて、
実践的かつ本質的な子育て方法を学べる講座です。
現代の子育て環境は非常に複雑で、孤立感や不安を抱える親御さんも少なくありません。
この講座では、そうした課題に寄り添いながら、親子ともに成長し、
より良い関係を築くための糸口を一緒に探していきます。
⑵ このようなお悩みをお持ちではありませんか?
●子育てに自信が持てない、常に手探りで不安を感じている
●子育てのストレスが夫婦関係に悪影響を与えている
●周囲に相談できる人がいない、または過干渉で気軽に話せない
●お子さんの集団生活への適応に不安がある
●コミュニケーション能力や自己肯定感の育ちに不安を感じている
●親子のどちらかが精神的に不安定で、サポートの方法が分からない
こうした悩みを一人で抱えず、講座を通じて安心して学び、相談し、解決の糸口を見つけていくことができます。
⑶ そらいろ子育て心理学講座の3つの特徴
特徴①:心理学に基づく本質的な子育てが学べる
そらいろ講座の最大の特徴は、心理学的アプローチに基づいた本質的な子育ての理解と実践ができることです。
単なるしつけや対応方法ではなく、お子さんの「協調性」「主体性」「自己肯定感」といった、
幸せな人生を生き抜くための力を育てる視点で学んでいきます。
特徴②:実績あるカウンセラーが構成したオーダーメイド型のカリキュラム
講座は、実際に数多くの子育て問題を解決してきたカウンセラーが構成しています。
お子さんが医療機関にかかっている場合も、医師の診断を尊重しつつ、
心理的なアプローチで補完し、実践可能な対策を一緒に考えていくことができます。
また、一般的な知識の提供ではなく、一人ひとりのお子さんに合わせた「オーダーメイド型」の視点を大切にしています。
特徴③:親子の成長を実感できる、継続的なサポート
受講者の多くが実感しているのは、講座を通じて少しずつ心理的な負担が軽くなり、
親子の関係が改善されるという変化です。
学びを実践に移し、繰り返し経験することで、自信が育ち、お子さんとの関係性にも好循環が生まれていきます。
「子育てに喜びを感じられるようになった」という声も多く寄せられています。
⑷ 実践的なテーマで、明日から役立つ学びを
講座では、毎回のテーマをできる限り具体的かつ実践的に設定し、
受講者ご自身のお子さんの姿を思い浮かべながら、具体的な解決策を学べる構成となっています。
「どうしたらいいか分からない」を
「これならやってみたい」
に変えるきっかけを提供します。
「そらいろ子育て心理学講座」は、子育てに悩むすべての親御さんに、
希望と安心、そして成長の道しるべをお届けする講座です。
一人で抱え込まず、まずは一歩踏み出してみませんか?あなたとお子さんに合った答えが、きっとここで見つかります。
最後に
心理学を知識として学ぶことは大切ですが、実際に活用し、成果を見出すことはなかなか難しいと聞きます。
もし、活用できてお子さんがどんどん成長したら、人生全体まで変えてしまうほどの大きな効果を得ることになります。
心理学を学び、それを日常的な行動レベルまで落とし込んで経験値を上げる。
そして、実際に実践し、成果を実感できるようになるのが本講座の特徴です。
皆さんも積極的にご参加いただき、心理学を活用した豊かな未来を作りましょう。
5.講座の流れ
〇講座の前半
毎回、心理についてのテーマを選定してお伝えします。発達心理学、社会心理学、人格心理学、スピリチュアル思想などからお伝えします。
テーマの講義と質疑応答になります。ここではなるべくたくさんの質問をしてください。質問した分だけ理解度が上がります。
〇講座の後半
新しく学んだことに対して、参加者の皆さんで話し合い、個人のお悩みの状況への対応や今回のテーマを日常的に活用する方法を検討します。
最後に日常的に行かすことができることを決めて、帰宅後の活用を図ってもらいます。
〇実施形態:
定期開催のグループレッスンとなります。欠席の場合、または、ご要望に応じてパーソナルレッスン対応も可能です。
〇おためし体験レッスンも可能です。その場合は参加費用が半額になりますので、
お気軽に参加し、判断することが可能です。
6.料金のご案内
⑴ グループレッスンの料金
グループレッスンの料金は以下のようになります。面談、オンライン、ともに同じ料金となります。
・6,600円(税込/一人、一講座ごと)
⑵ 個人レッスンの料金
個別レッスンの場合の料金を以下にご案内致します。面談、オンライン共に同じ料金となります。
・ 6,600円(税込/60分)
・ 9,900円(税込/90分)
・13,200円(税込/120分)
7.お申込み、お問合せ
●講座のお申込み、お問合せにつきましては
ページ下部のお問合せコーナーからご連絡をください。
どうぞ、お気軽にご質問なさってください。
●そらいろ心理学講座 事務局 山中 聡子
お電話:080-4201-6121
8.体験談
現在、工事中となります。m(_ _)m
9.過去の講座情報 そらいろ心理学講座
そらいろ心理学講座の過去の講座の一覧を以下にお伝えします。パーソナルレッスンを受講できますのでご希望の場合はおっしゃってください。
タイトル右側にある下向き三角ボタンをタップ(クリック)すると講座の概要を確認できます。
今回は怒りという感情を取り上げてみたいと思います。
怒りをぶつけられると、その結果として悲しみ・無力感・孤独感・罪悪感・失敗の恐怖・劣等感などの感情が生まれ、やがては絶望感そしてメンタル不全へとつながります。
怒りを理解し、どうしたら健全性を回復できるのかを皆さんと考えてみたいと思います。
個人の意識が集まった大きな意識の状態を知ると、自分はどう生きたらいいのかがわかります。
特に時代の激変期には集合意識が揺れ動くので、不安が大きくなり、間違ったものを指標にしがちです。
意識の流れを縄文時代までさかのぼり、未来の予測も行い、振り返って自分がどう生きたらいいのかを理解しましょう。
今回は条件反射で人生がつらくなるパターン、そして成幸するパターンを皆さんと考えてみたいと思います。
条件反射には実に様々な個人の経験からくる価値観が反映されています。このパターンを理解し、その変え方を知ることができたら、人生は素晴らしいものになります。
ぜひ皆さんと考えてみましょう。
今回は不安と恐れ、について考えてみましょう。双方の違いを深く理解しますと、心の使い方の癖、あるいは大切な人の辛さが良く理解できます。
また、病気やつらい状態との向き合い方も整理ができます。そして具体的な対策についてもお伝えします。なくすことができない不安への対処法を皆さんと学びましょう。
辛さが軽くならないのは、トラウマの除去と、認知の修正がうまく機能しないからです。
この改善を効果的に進める方法として対話法があります。今回は、本人もあまり意識しないうちに心の癖が変化してしまう対話法を皆さんと学んでみたいと思います。
会話の修正で認知の修正ができるのなら素晴らしいですね。
イメージ療法を体験して頂き、イメージでつらさを除去しただけなのに、なぜ効果が上がるのか不思議に思う方もおられると思います。
そこで、今回はイメージ療法の種明かしをしてみたいと思います。しくみを知ると、病や辛さの状態が回復しにくい理由がわかり、そして、成幸への道のりも早まります。
前回はトラウマを削減する方法を試してみました。今回は、未来を見てみましょう。
私達は一生懸命勉強したら幸せになれると教えられてきましたが、実際には大分違います。具体的にどうしたらいいのか、未来の自分に聞いてみる体験をしてみましょう。
意外な答えがわかるかもしれません。
私たちを苦しめるトラウマ、これは、通常の心理アプローチでは少しづつ削り取るように減らします。
しかし、イメージ療法では、割と大きく削ることができます。その仕組みはどうなっているのか、そして、どうしてそんなことができるのか、をご理解頂き、実際に一度体験してみましょう。
共依存は、アダルトチルドレンや各種依存症、様々な精神疾患や嗜癖(しへき)と関わりのある心の状態です。病気でなくても、日常の生活のかなり広い範囲に影響を及ぼしています。
依存と、共依存の違いも含め、原因と対策を一度しっかりと理解すると、心理的な改善を目指せると思います。新たな発生防止効果も含めて学びましょう。
心の健康を脅かし、人間関係や幸福感、ひいては人生にも悪影響を及ぼすのがトラウマ、あるいはPTSDと言われるものです。
それぞれの意味の理解はもちろんですが、原因と対策を知り、改善、回復に努めたいと思います。充実した人生を取り戻すためにも、十分に理解し、実践できるようになりましょう。
悩みがある時、私たちは落ち込んだり、自分の人生を恨んだりすることもあると思います。
この状態、どうしたら安定するのでしょうか。それには、安定の状態と不安定の状態を理解することが大切です。
そうすれば、自分だけでなく、関わる周囲の方の安定も実現できます。どうしたらいいのかをみなさんと一緒に考えてみましょう。
今回の心理講座は子育てで取り上げた、分岐点における葛藤の一般社会編として実施します。
夫婦関係、会社の人間関係、親族間でのトラブル、など様々な人間関係のトラブルが発生しているとき、対策の選択によって、私たちは、自閉、諦め傾向、依存傾向、自立傾向に向かうことになります。
理解し、大きく成長に結び付けて参りましょう。
今回は死生観について皆さんと考えたいと思います。
死ぬ事があるからこそ、生きる事の意味が鮮明になるという考え方です。この死生観、良い形で持っている人と、そうでない人では、人生の広がりに大きな差が生まれます。
今後の人生をよりよく生きるためにも、皆さんの健全な死生観を考えてみましょう。
回復の過程において、自分と相手の主張との間の妥協を見出す協調性の回復は不可欠です。しかし、そのブレーキになってしまうのが、反論の形成不全となります。
反論の形成ができないのはどうしてか、形成不全だとなぜ回復しないのか、どれだけ人生において重要なのかをみなさんと理解し、対策を確認しましょう。
お悩みが長期化するには相応の理由があります。
お悩みというのは、ストレスが強く、対処できない事から始まるのですが、ストレスの発生する環境がなくなっても、心の中に反射という状態でいつまでも残ることになるのです。
この反射を取り除くためには主体性と自己愛が欠かせないのです。今回はこの部分を皆さんと話し合ってみましょう。
辛い状況というのは、自分に蓄積した様々な認知の状態によって引き起こされます。
この認知の状況を血液型、エニアグラムなどのパターン分類ではなく、更に詳しく、個別の状況による分析を行い、感情の状態を知ると、自然に取説のようなものが見えてきます。
自分の行く道はどの方向なのか、一度しっかりと理解をしてみましょう。
意識領域が狭いことにより、トラブルが発生することはご存知と思います。
具体的にはPDCALを使って繰り返しの振り返りで少しづつ広くすることが順当な方法ですが、大きく広げる方法もあります。
難易度が高いのですが、もしかしたら大きく前進することも可能です。今回はこの方法を皆さんと体験してみたいと思います。
引き寄せ、願望実現という言葉はありますが、簡単と思う人と、難しいと思う人がいると思います。
その違いがわかると、なかなか回復しない、楽にならない、という方も大きく前進できるのです。
具体的なステップがあれば私たちの願望実現はシンプルな作業の連続へと変わっていきます。今回はこの点を皆さんと学んでみましょう。
今回は主体性を発達させるための手法を取り上げてみたいと思います。
私たちはとかく、白黒をはっきりとつけて、対策もきっちりと決めることを重要視しがちです。しかし、このやり方には人が成長しにくくなるデメリットがあるのです。
精神疾患、対人関係の苦手意識、自信喪失、これらを改善するためにも、みなさんと考えてみましょう。
前回は、辛い状況から回復する事について学んでみました。今回は、成長について、取り上げてみたいと思います。
成長期とはどういうものか、を振り返り、成長させる方法、具体論、そして体験をみなさんと共に感じてみたいと思います。
定着したときにどんな素晴らしいことが起こるのか、みなさんと体感してみたいと思います。
メンタルが不調な方が回復するまでには大きく分けて二つの領域があります。健全領域に於ける回復と、不健全領域に於ける回復です。
これらをすべて理解し、少しづつ取り組んでいくと、再発の心配のない健全な状態、明るくて前向きな状態が実現できます。
その条件を知り、具体的に何が不足しているかを理解し、次の一手を学びましょう。
予期不安と強迫観念、似たように思えますが、意味が違う別々の心の癖です。この二つを理解し、対策することができると、心の健全度はずいぶんと向上します。
この二つがあるだけで人生においてどれだけの損をしているのか、計り知れません。今からでも、間に合う、実践的な解決方法を身につけて参りましょう。
今回は対人関係が苦手な人の関係性と、苦手でもないけど、不健全になってしまう不適切な関係性を見つめてみたいと思います。
双方の悪化の流れの理解と、その改善の流れの理解を、皆さんと深めたいと思います。対人関係は、一生を通じて発生するものですので、しっかりとご理解を頂き、活かせる自分を育てましょう。
人生において、良くならない生き方というのが心理学的にもはっきりとあります。
その生き方をしていると、病になりやすい、回復しにくい、幸せを実感しにくい、そして自信が身につきにくいという、大変困った人生になってしまいがちです。
今回は心の癖の一つである、はじっこあるき、という心の癖を学び、対策を検討してみましょう。
今回は全人格性についてとりあげてみます。不健全な人、健全な人、幸せな人の全人格性はどうなっているのかを知りましょう。
そして、全人格性がどうなっていると病んでしまうのか、どうしたら解決の方向に向かうのか、そして、どうなったら幸福に近づけるのかを皆さんと考えてみましょう。
人間関係の苦手意識は、テクニック不足の問題と思われがちです。実際に上手に話せる方法や、駆け引きをする方法を教えて欲しいというご要望は多いものです。
しかし、お伝えしても良くならないことは、よくあるものです。実はその原因は意外なところにあるのです。これを理解すると関係性の悪化の本質が見えてきます。
心理に安全でない家庭で育つと、お子さんは柔軟性不足、予期不安、強迫観念、感情鈍麻などの状態が発生し、長年苦しむことになります。
こだわりが強かったり、自然なコミュニケーションが取れなかったり、様々な影響があります。放置しても改善しないため、回復させる必要があります。
今回は、影響と対策について、学んでみましょう。
今回は、願望実現を心理的に理解しましょう。
三つのステップがあり、このステップの特徴を理解すると、なぜ、願いが実現しにくい人としやすい人がいるのか、分かってきます。
宗教上の祈りの効果は、心理学的に最も効果がある願望実現と似ているのです。最も効果のある願望実現を皆さんで理解し、活用するイメージを作ってみましょう。
私たちの精神は状態によって、フォーカスする範囲が変わってきます。
カウンセリングの時、不安な時、楽しい時、なれない知人との会話の時などで、フォーカスする範囲が変わってきます。
この変化を図を使って説明し、具体的な対策もお伝えしたいと思います。不安な状況を健全な状況に育てるためにどうしたらいいのかを考えてみましょう。
今回は、精神疾患の状態もしくは、辛いお悩みの状態の方がどういうステップで回復をするのかを学んでみたいと思います。
まずは各ステップの特徴の把握し、そのステップをクリアするのに必要な要素を理解します。皆さんの回復への課題の絞り込みと対策の導き出しを実施してみましょう。
前回に引き続き、感情の状態と他者とのかかわりを図式化して理解してみたいと思います。
今回はネガティブな感情だけでなく、ポジティブな感情についても図式化してみたいと思います。
この図式を理解していると精神の健全化、そして発達に対し、とても重要なことを理解できることになると思います。みなさんで深めてみましょう。
人や自分の事をネガティブに思う事は良くない事と一般的には言われます。
しかし、どう良くないのか、そしてどう考えたらいいのか、私たちはあまり、詳しく理解ができてないと思います。
今回は、どういう問題が発生し、どういう解決策があるのか、を皆さんと考えてみたいと思います。大きく人生を変えるヒントが見つかると思います。
今回は依存と禁断症状についてを取り上げてみようと思います。
麻薬、アルコール、薬物、ネット、お菓子、辛いもの、ゲーム、買い物、恋愛など、様々な依存があり、禁断症状もあります。
今回はなぜ依存が発生するのか、なぜ、回復しにくいのかを理解し、禁断症状の対処と対策について、みなさんと学んでみましょう。
なぜ、防衛機制が必要になるのか、そして自分にはどのような防衛機制があるのかを、事例分析を使い、解明し、この防衛機制とどう向き合い、どう、解消して行くと良いのかを皆さんと考えてみたいと思います。
防衛機制はゼロにすることが重要なのではありません。どう協調するのが良いのか、が重要なポイントになります。
変わりたい、成長したい、健全になりたい、と思う事、あると思うのですが、本人に意欲がないとなかなか難しいですよね。
本人に意欲がなくてもその気になる会話術があると便利ですよね。
そんな会話術、今まで学んできた心理学を上手に応用すると出来るのです。意欲の出る会話術、皆さんと考えてみましょう。
人生には大小さまざまな分岐点がありますが、この分岐点で間違った道を選ぶことが重なると、後戻りできない状態になります。
そして、その分岐点は自分が当事者だとわかりにくい特徴があります。
仕事、恋愛、メンタルの回復など、様々な場面で大きな影響を与える分岐点とはどういうものかを学び、人生を大きく変えて行きましょう。
私たちを苦しめる心の癖、ネガティブな承認欲求ですが、大別すると2つの時期、2つの状態があります。
前期、後期、陰性症状、陽性症状です。今までは比較的前期のことをお伝えしてきましたが、なかなか難しいのが後期です。
今回は、後期にまで回復した人をどうやって健全な形で自立に向かうのかを学んでみましょう。
セルフイメージは自己認識とも言います。このセルフイメージによって私たちは苦しめられてしまうのです。
この苦しみが形成されるしくみと改善される仕組みを知ることができると、人生は好ましい変化を始めます。
今回はこの変化をどうやって起こすのか、を皆さんと考えてみましょう。小さな行動が大きな未来の変化を引き寄せてくれます。
人間関係が安定してしっかりとしていると、とても穏やかで、前向きで明るい日々を送ることができます。
また、多少の不安や失敗があっても、落ち込まず、悲観せず、自己否定になりにくくなります。人間関係をしっかりと築くことができる人って何が違うのでしょうか。
今回は安定した人間関係を築く事について皆さんと考えてみましょう。
私たちの心の健全度は大別すると5つに分けられます。
この状態を理解し、適切な対応ができると、ストレスにも強くなり、成長もでき、更には自信も育てることができます。逆に、このステップを無視して育てようとすると、とても反抗的になったり、大きな反動が出ます。
今回は、この健全度のステップを皆さんと考察して診ましょう。
今回は、辛い気持ちを整理しやすい方法を皆さんと体験してみたいと思います。
立場的視点と表層、深層の視点から整理できる方法がありますので、これを実施してみたいと思います。
短時間に整理できるということは、モヤモヤを理解しやすくすることができるので、長時間、辛い思いを抱えることも減ると思います。一緒に考えてみましょう。
今回は感情の状態から引き起こされる負の連鎖について考えてみたいと思います。
プラスに見える感情であっても、やりすぎると負の側面が発生します。この関連性を知っておくのと知らないのでは大きな違いがあります。
プラスの側面を理解し、そしてマイナスの側面も理解してみましょう。最後に対策も検討したいと思います。
今回はトラウマの後編になります。
トラウマの回復というのは多くの人に取って大切なことではありますが、この回復に関しては多くのノウハウが書籍やネットで拡散してるのですが、なかなか回復率は上がらないものです。
今回はその原因を皆さんとしっかりと確認し、回復の方法をしっかりと身につくようにしてみたいと思います。
私たちが体験した育児はあるべき姿を目指す育児と言えます。この方法には深刻なデメリットがあります。
これを理解すると、今の自分の抱えている苦しみを今までと違う角度から理解できます。そして、その対策を知ると、今抱える苦しみからの回復に加速がつくかもしれません。
ぜひ、皆さんとご一緒に考えてみましょう。
今回はトラウマと向き合ってみましょう。
健全な生活を脅かすトラウマとはどうやって発生するのか、心にどういう影響を与えているのか、なぜ、回復しにくいのか、そして、どうしたら回復するのかを学んでみましょう。
まずは前編としてトラウマの発生する経緯、受容、癒しまでを取り上げます。後編では回復までの流れを取り上げます。
私たちの様々な選択は実は大いに心理によって影響を受けています。食べるもの、食べる量、洋服、クルマや家電などの耐久消費財、そして住宅までもです。
心がどのような時にどのようなものを選ぶのか、そして、どう選んできたから私たちの今があるのか、そしてどう選ぶと新たな人生が切り開けるのかを皆さんと考えてみましょう。
私たちの劣等感は他人との比較で優劣を感じるところから始まります。結婚するのが遅い、出世するのが遅い 身長が低い、などです。
そして、それは定年後まで続きます。これでは、幸せの定義は他人に勝つということになってしまいますね。
今回はこの比較優位の考え方をどう考えたら自分らしい幸せになるのかを考えてみたいと思います。
心が不健全な時、一般的には行動療法的な考え方を選ぶ人が多いものです。
しかし、実際には効果が上がりにくかったり、逆効果になっていることが多いものです。しっかりと効果が出るためには、本質的な理解とが必要です。
本質的な理解と対策とはどのようなものか、本質的な対策とは、どうしたらいいのかを今回は考えてみましょう
人間関係や業績不振により私たちは悩んだり、落ち込んだりします。長期間にわたると人格にまで悪影響を及ぼし、反抗的になったり感情的になったりもします。
このような状況から回復するのにとても大切で尚且つ、大きな効果的なのが今回のテーマです。どのように考え、日常の生活に取り入れるのか、具体的に考えてみましょう。
感情というものは空気のようなもので、心という部屋にあると、必ず混ざってしまうものです。
混ざると灰色に近い色になってしまいがちです。メンタルがつらいときは、少しのネガティブな感情も増幅してしまい、心の中が灰色から、黒に近いような色になってしまいます。
どうしたら、気持ちの良い色に戻せるのかを今回は考えてみましょう。
センタリングとは本来スピリチュアルにおいて使われる概念です。
傷ついた心のバランスをとる手法でありますが、今回はこれを心理学的、そらいろ的にアレンジします。
みなさんの心のバランスのとり方を心理学的に分析してみたいと思います。どのような状態になっているのかを知ることは、よりよく生きることのためにとても大切なことですね。みなさんと考えてみましょう。
人間関係の改善には互いの自己愛の状態が大きく影響します。自己愛の状態が良いと関係性が改善しやすくなります。また、状態が良くないと、改善しにくくなります。
自信、未来への楽観度などが悪化するので、相手を判断するときにも悪影響となります。そしてこの状態が相手に伝わるのです。この対策を検討し、より良い人間関係を構築しましょう。
私たちは、良くなりたいと願いながら日々を過ごしています。
自己啓発書にも、行きたい道を見つめるように、と書いてあります。しかし、その思考はやる気、元気が十分の時に限られるとのです。
対極という新たな視点を皆さんと共有することで少し違ったものが見えてきます。本当の強さ、健全さ、幸福度とは、一方を知るだけでは成り立たないのです。
私たちの人格はキャラクター同士がぶつかることによって成長します。
しかし、パーソナリティをたくさん使う環境に育ったりすると、なかなか、本来育つべき人格が育つことができなくなります。
そして相手のキャラクターと自分のパーソナリティのぶつかり合いなどで傷ついてしまうこともあります。
この時心に何が起こっているのかを知り、対策を知りましょう。
今回は潜在意識領域まで使った、メンタルトレーニングを皆さんとしてみたいと思います。
私たちの意識はどうしても過去のトラウマや癖を引きずったまま成長するので、バランス良く成長することが難しいのですが、整理して刺激をすることでバランスが整いやすくなります。
どのようにしたらバランスよく成長するのかを皆さんと考えてみましょう。
生きるのが辛いという状況は、別の言い方をすると、必要とする意識領域の広さを自分が現時点で有してないということになります。
この意識の広さ、狭さはどういう心理によって成り立っているのかを今回は取り上げてみたいと思います。
今の自分に必要とされている広さをどうやって知るのか、それを広げるためには何をしたらいいのかを考えてみましょう。
問題が改善しやすい状況としにくい状況に分けた場合、改善しやすい場合に共通することとして自己愛の状態があります。
影響を大きく与える人の自己愛の状態が健全ですと、相手に与える安心感や信頼感が好転し、信じれば良くなるという感情がわいてくるのです。
こうならないときは反対に関係性が悪化します。対策も含めて詳しく理解してみましょう。
私たちは対策やノウハウをたくさん学びますが、あまり成果に結びつかない時もあります。その理由は、現状の理解と受容が不足してるのからなのです。
そのため、抵抗、敵対、憎悪を生み出してしまうのです。深く広い受容が私たちの日常をとても肯定的かつ発展的にしてくれます。
今回は、問題を解決し、より良い未来を作るための心理的方法を考えましょう。
世の中には様々な占いなどがあり、それを使って相性の判断が行われておりますが、似たようなことは心理学でもできるのです。
心理学的視点を使って、夫婦、恋人、親子、兄弟、友人、上司部下の関係などをある程度診断することが可能です。
今回は心理学的にみた相性の診断と対策についてみなさんと考えてみましょう。
私たちは、誰もが良い人生を送りたいと希望していると思います。
しかし、前向きとか、肯定的とか、言葉はとっくに知っているのに、なかなか実現できないでいることが多いものです。
今回はこれを具体的にワークショップとして皆さんと考えてみようと思います。自分の人生を少し主体的に変化させると、少し以上の結果につながるのです。
お悩みや精神疾患には様々な分類法がありますが、今回は自立している傾向のお悩みと依存傾向のお悩みという分類で考察してみたいと思います。
精神疾患やお悩みは自立性が高い状態と依存性が高い状態では、取り組み方が変わります。回復の過程も変わって参ります。
新しい視点からの回復への道のりを皆さんと理解して参りましょう。
毛髪を指に巻き付けるのは…とか、唇を噛むのは…など行動にはそれなりの心理的背景があります。
一つ一つを知識として覚えなくても、その背景を推測することはできます。
今回は行動と心理的背景の関係を知り、コミュニケーションにどう活かしていくのかを皆さんと深めて参りたいと思います。コツがわかれば、対人関係が楽になると思います。
今回のテーマは、ネオテニー進化論です。
ダーウィンの進化論では説明のつかない部分を補うのがこの進化論とされてます。幼形進化ともいわれ、なんと日本人はこの進化においてはかなり進んでいるともいわれているのです。
理解し、実践できれば、肯定的で豊かな人生を送ることができるこのネオテニー、皆さんと人生をより楽しく生きて参りましょう。
従属性中心はよくない、主体性を育てることが大切ですね。
しかし、ここを具体的にどうするかについて今一歩、閾値越えができないで困っている方が多いようです。
今回は従属の状態と主体の状態を詳細に理解して頂き、変化する瞬間を皆さんに理解してもらいたいと思います。
この変化の瞬間がわかったら、前進する速度が大きく変化すると思います。
私たちが日々感じている感情は数十もあります。
不健全な時、そのうちの一つだけに集中することがあります。悲しみ、つらさ、不安、そして反対もあります。快楽などです。
これらの集中が、心の病みの原因になります。今回はこの不健全な状態を具体的に回復するワークショップを実施してみます。
皆さんの心がほぐれる体験をしてみましょう。
日本人は欧米諸国だけでなく、隣国である韓国や中国と比較しても肯定感が低いとされています。
精神年齢が低い大人の増加が精神疾患の増加、引きこもり、犯罪の増加の原因ともいわれています。
その背景を知り、精神的に追い込まれていきやすい考え方や、ひとたび病になるとそこから抜け出しにくい認知を理解し、具体的な対策を検討しましょう。
病が治りやすい人と治りにくい人は何が違うのでしょうか。また、同様にお金に苦労する人、しない人もいます。
そして、そのどちらの根源も似ているということが最近わかってきました。
病が回復しやすい人は、どう違うのか、お金に苦労しない考え方とはどのようなものか、このことを皆さんと一緒に考えて参りましょう。
承認欲求、特にネガティブな承認欲求はとても大きな影響を人生に与えます。
このネガティブな承認欲求に対抗するために自己承認は欠かせません。楽に生きるにも、成幸した生き方をするためにも、自己承認力は不可欠です。
今回はこの承認力を実際に皆さんで育てるワークを体験し、知っていることとできることの違いを理解しましょう。
世の中には望んだ結果を手に入れることが簡単にできている人とそうでない人がいます。
その差は少しなのですが、時間が経過すると埋めがたい差になります。一体何が違うのでしょうか。
今回は望んだ結果をなかなか得られない方の事例をもとに、結果が手に入る心理について語ります。
皆さんもよい機会ですので結果が手に入る心理を身に着けましょう
コンビニ業界ではセブンイレブンの心理学という言葉があるくらい、トップ企業では心理を重要視しています。
また、辛い人生を歩む方は、これをすると失敗するという轍を踏んでいる事が多いのです。心理の理解の仕方一つで仕事、収入、人生の充実度まで大きく変化します。
自分の人生を大きく左右する哲学的心理を皆さんと話し合ってみましょう。
プライドが高い、という言葉、良く使われていますね。反省すべきことをなかなか反省できなかったり、素直に認めるべきことを認められなかったりするときに使われます。
本来のプライドは誇りですが、最近では恐れの大きさとして使われているようです。
このプライドが高いと人生の幸福度は下がります。しくみと対策を皆さんと考えて参りましょう。
ネガティブな承認欲求は小さな子供から、大人まで日常的に使うものです。そして無意識に使う時と意識的に使う時があります。
中でも根が深いのは、無意識に使ってしまうもので、これはなかなか回復することが難しいのです。
この対策は小さなころの未処理の課題が発生するときの様子がヒントになります。皆さんと考え、根本的に回復させましょう。
人生のいろいろなところで、はまってしまったように困った状態から抜け出せない事ってありますね。
そのはまってしまった状態はどうしてそうなるのか、そして、どうしたら、そこから抜け出せるのか、を今回は考えてみたいと思います。
思考パターンとはまりパターンを分析し、そこから抜け出せる方法を考えてみましょう。
人生を良いよく生きるために、辛さや恐れを取り除くために、様々なノウハウ本が出版されていますね。
しかし、そのような知識がなくても、とても素晴らしい、ナビゲーターがあります。そのナビの活用の仕方を皆さんと考えてみたいと思います。
この活用方法がわかると、私たちはあまり本を必要としなくなり、自信もついてくると思います。
私たちのお悩みの大半は人間関係に起因すると言えますが、その人間関係を改善しようとしたとき、苦手意識を克服しようとするとき、私たちが実施している対策は実は間違っていることがわかりました。
本当にすべき対策とは何か、今回はそれをお伝えしたいと思います。これを抑えておけば、これからの人生、安心です。
人生を素晴らしいと思って過ごす事はなかなか難しいですね。しかし、実際にそう感じて生きている人も少なからずいる事もまた、事実です。
なぜ、素晴らしい人生を手に入れるのは難しいのでしょうか。そしてどうしたらそれが実現できるでしょうか。今回は皆さんと心理のありようを考えてみたいと思います。